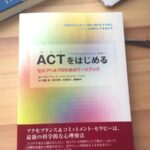希望とガッカリと
自分の中の問いと
たくさんの感情を感じた1日
坂上監督は、
「『プリズン・サークル』の舞台は刑務所だが、「これは刑務所の映画」ではない。語り合うこと(聴くこと/語ること)の可能性、そして沈黙を破ることの意味やその方法を考えるための映画だと思っている」
何度も見たい、そう感じる映画作品。
映画の中、いままで言ったことがない話を話されるシーンがあったが、そこに至るプロセスを講演会にて、坂上監督から聴けたと、同時に、
「映画はプロセスが抜け落ちてしまう」
そして、支援専門職員さんがおられない、自由時間の 中で、お互いに対話する時間があり、これが「要」だとの話も聴けた。よかった。
対話の力
そして、お互いに対話の場をファシリテートする力か育まれている
まさに、この形だと感じた。
僕の純粋感性は
「なにもしない」なんだけど
この「何もしない」が、肝に繋がった感じ。
そう、見守るけど、中心は自分じゃない。
と、こんな感じ
これらから、希望を感じたが
一方で、
この取り組みは、島根の1箇所のまま。
アメリカは再犯や大きな罪の方を対象としているのに、
日本は、初犯の方にフォーカスしている点、TCから社会復帰した方を支援者に入れる気がなさそうな、事勿れ主義に、ガッカリ、いや、絶望を感じた。
個人的なことだが
スクリーンの方々と、自分は何が違うのか、
僕自身、あと一歩で、、と激しい衝動と憎悪に飲み込まれたことがある。
やらなかったのは、単純に、
距離が離れていたから
鳥取へ大阪から行ってやる、となるまえに、
憎しみと怒りに飲み込まれたけど、
関わってくれていた
弁護士さんから
「民事は支援するけど、君の刑事事件を弁護はしないからね」と
励ましの言葉で踏みとどまれた。
ほんのちょっとした違いでしかない。
あと、映画を見ているなかで
自分のトラウマ、からだのトラウマがあることに気づいた。
気づいたということは、飲み込まれてない。
そして、そこから
最近、反応してしまう自分のパターンの大元にある
思い込み(自動思考パターン)、いわゆるビリーフに気づいた。
ほんとうに、それ前提で生きていたことに気づいた。
気づいたらもうビリーフじゃない。
もっと自分を自分で丁寧に大切に歩いていこう、そう感じた。